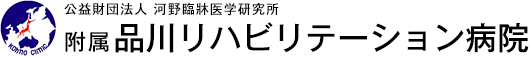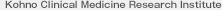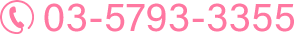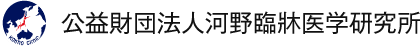勉強会 【認知症患者の理解と対応方法】

東京医療保健大学 医療保健学部看護学科 阿部桃子教授をお招きし
ご講義いただきました。
〈講義内容〉
1 代表的な認知症と治療
2 BPSDのメカニズム
3 治療の場における認知症当事者の主観的体験に沿ったケア
医療・介護において、認知症の理解は必要不可欠となっております。
看護・介護、リハビリ、いずれの関わりにおいても
認知症の症状を有する方を、理解しようとすることから始まり
関わり方、接し方、表情・声・言葉遣い・言葉のかけ方次第で
良い方向にも、良くない方向にも影響することを、あらためて学ぶ機会となりました。
決して簡単なことではありませんが
職員ひとりひとりが、その方その方に合わせた関わりができるよう
努めていきたいと思っております。
ご講義いただきました。
〈講義内容〉
1 代表的な認知症と治療
2 BPSDのメカニズム
3 治療の場における認知症当事者の主観的体験に沿ったケア
医療・介護において、認知症の理解は必要不可欠となっております。
看護・介護、リハビリ、いずれの関わりにおいても
認知症の症状を有する方を、理解しようとすることから始まり
関わり方、接し方、表情・声・言葉遣い・言葉のかけ方次第で
良い方向にも、良くない方向にも影響することを、あらためて学ぶ機会となりました。
決して簡単なことではありませんが
職員ひとりひとりが、その方その方に合わせた関わりができるよう
努めていきたいと思っております。
*BPSD
「行動・心理症状」 または 「周辺症状」
病気の進行に伴い、認知機能が低下したことによる「中核症状」に加えて
環境や周囲の人々との関わりの中で、感情的な反応や行動上の反応が症状として発現する。